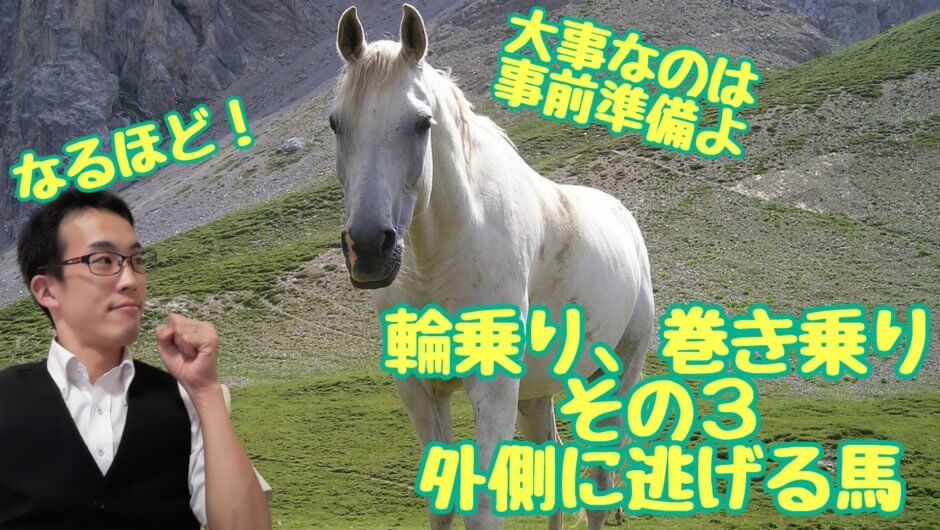輪乗りや巻き乗りをしたいのに曲がってくれない!やっと曲がったと思ってもすぐ外に戻っちゃう。どうすれば良いの?
そんな悩みにお答えします!
今回は、輪乗りや巻き乗りの最中、外側に逃げていく馬について解説しますね!
なお、この記事は「輪乗り、巻き乗りを覚えよう!」シリーズの第3弾となっています。第1弾、第2弾はこちらからご覧ください。
この記事のもくじ 閉じる
馬が外側に逃げる理由

結論、輪乗りや巻き乗りで馬が外側に逃げる理由は、「楽をしたいから」です。
これだけ聞くと、内側に切れ込む時と同じ理由だと思うでしょう。
ですが、内側に切れ込む時と外側に逃げる時では、明確に違うことが1つあります。
それは、内側に切れ込むのが、「指示を聞いてるけど楽をする」なのに対して、外側に逃げるのは、「指示を聞きたくないから、逃げる」だと言うことです。
輪乗りと巻き乗りに限定した場合、僕たちは「曲がって」という指示を出してるわけですね。なので、内側に切れ込むのと外側に逃げるのでは、指示に対しての反応が違っています。
結局やる事は「馬のサポートをしてあげる」なんですが、微妙にその対応が変わります。1つ1つ、解説していきましょう。
外側に逃げていく馬の対策

外に馬が逃げていく場合の対策は、以下の4つになります。
- 外側の手綱や外方脚でフタをする
- 口だけで何とかしない
- 早めの対応
- 乗り手がバランスを変えない
解説していきますね。
初心者レベルの輪乗りの場合、多くの馬は肩から外側に膨らんでいきます。
なので、首だけ一生懸命内側に向けていても肩が外側に流れれば、馬は外側に逃げてしまいます。なんとかして前肩を外に出さないようにしないといけません。
そこで使うのが、外側の手綱と外方脚です。首の根元から前肩にかけて、馬にふたをしてあげましょう。
馬の前肩を押し戻したいので、外方脚はいつもより靴一つ分くらい前で使います。かかとだけではなく、べったりと足全体を押し付けるイメージです。
また、外側の手綱は最初は添えるだけで大丈夫ですが、馬が膨らんできたら、その分だけ押し戻してあげましょう。
この時に内側の手綱の張りがないと、外側のハミだけが引っ張られ、馬が右を向いてしまいます。結果、余計に外側に逃げてしまいます。
あくまでも、内方姿勢を作った状態で行って下さい。
※内方姿勢についての記事はこちら!
個人的には、内1.5対外1くらいの強さで手綱を持つと良いと思います。馬にとって苦しい回転を、僕たちがサポートしてあげましょう。
ここで難しいのが、口への指示だけで対応しないという事なんですね。
内側に切れ込むにしても外側に逃げるにしても、馬は求められた姿勢をとるのが嫌だから、違う行動をしているわけです。
それなのに人間がもっと苦しいプレッシャーを与えても、馬は余計に逃げていきます。
手綱を思い切り引っ張って口だけに圧をかけるのは、まさにその1つです。間違いなく馬の状態はもっと悪化するでしょう。
相手が人間だったら、同じ事はしないと思います。
耳だけを引っ張って、そこら中を連れまわすような事はしませんよね。肩を貸すなど大きい範囲でサポートしますし、なんなら全身を持ち上げちゃうのが一番手っ取り早く動かせるじゃないですか。
もっと曲がってほしいからと手綱をより強く引く。考え方としては間違いではありません。
ただ、手綱だけで全てを何とかする事が間違いなのです。先程言ったように、馬の胴体操作にも視野を広げましょう。
他の誘導の項目でも言ってますが、馬が完全に体重を乗せた後に何とかしようとしても、400kgの体重を動かすことは出来ません。
しっかりと体重を乗せた傾きに入る前に、早め早めの対応をしておきましょう。
イメージは電車のレールです。一気に急カーブをするのではなく、一歩ごとに少しずつ曲げていきましょう。
最初こそ気づけないかもしれませんが、余裕を持てれば確実に反応は出来るはずです。まずは優しめな馬から練習していって下さい。
誘導の操作は、腕を左右に開いたり閉じたりする必要があります。
結果として手綱だけに集中すると、バランスが崩れてしまうという事も有り得る話です。
左に傾いてしまっても右に傾いてしまっても、どちらも馬の真っ直ぐな走行には悪影響です。慌てずに小さな動きでコントロールできるよう、人も馬も準備をしておいて下さいね。
人は手綱を張ったり基本姿勢を見直したり。馬は脚への反応を高めておいたりできますよ。
左右のバランス確認については、こちらの記事をご覧ください。
まとめ!
今回は、外側に逃げる馬についての原因と対処法をお話ししました!
どの誘導にも共通して言える事ですが、大事なのは僕たちの事前準備なんですね。
馬が苦労する分を先に知り、僕たちがそのサポートをしてあげる事で、初めて見返りとして指示を聞いてもらえるようになります。
前回も同じ事を言いましたが、馬がどうなってれば動きやすいのかを考えた上で、騎乗できるようになりましょう。
ご覧いただき、ありがとうございました!
その4はこちら!