
内側にも外側にも逃げなくなったけど、相変わらず輪乗りや巻き乗りで、綺麗な円が描けない…。なんでだろう?
そんな悩みにお答えします!
第4回は、内外に行く馬ではなく、乗り手に原因があってキレイに回れない場合です。
今回は、どうしたらキレイな円をかけるようになるのか、お話をしていきたいと思います。
なおこの記事は、「輪乗り、巻き乗りを覚えよう!」シリーズの第4弾となっています。これまでの記事はこちらからご覧ください。
この記事のもくじ 閉じる
綺麗な円を描くためには
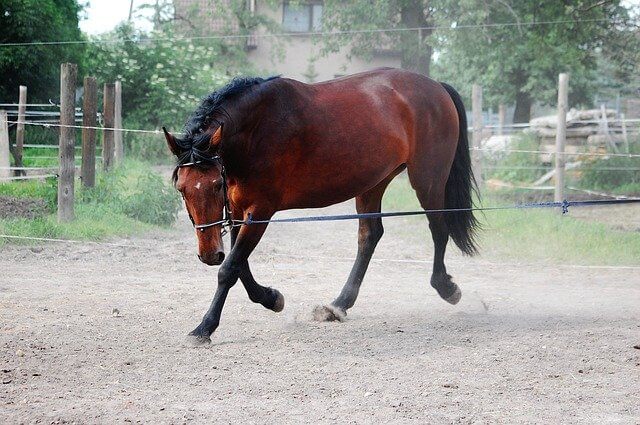
結論だけ言うと、円をキレイに描くために必要なのは、「自分の基準を持つ事」です。
個人的にふと思うんですけど、輪乗りや巻き乗りが出来ないという人でも、自転車で円を描いてって言ったら出来ると思います。
となると、自転車と馬って何が違うんでしょう?
それは、馬はバランスが一定じゃないという事です。
馬は曲がる時、脚を大きく開いて曲がる事も出来ますし、小股で曲がる事も出来ます。機械じゃないので、毎回同じ曲がり方をする習慣は無いでしょう。その時の曲がりやすい形で曲がってます。
「曲がって」という指示ではなく、「体をこれくらい傾けて、これくらいの角度で曲がってね」と人間が指示しなければ、馬はキチッと曲がる理由はないんですね。
ただ「歩いてね」と指示されたにも関わらず、歩いてみたら「どうして行進しないんだ!」と言われてるようなものです。
そのためには、これくらい曲がるにはこれくらいの指示をすれば良いのねという、自分の基準が必要になってきます。解説していきますね。
自分や馬の基準を知るための考え方

自分や馬の基準を知るための考え方は、以下の4つです。
- 指示の形を変えずにいられる場所を探す
- 両方の鐙と、お尻に掛かっている体重を意識する
- 手綱は短く持つ
- 難しかったら細かい四角形と考えてみる
解説していきますね。
先程は自転車の例えを出しましたが、その上で皆さんに質問です。
自転車で円を描く時、ハンドルって細かく操作しますか?
…しませんよね。最初から最後まで、同じ形で回り続けると思います。
初心者の方の多くが、「勝手に馬が曲がっちゃった」という部分に過剰反応し、けっこう左に右にちょこまかと対策をしてくれます。
ただ、それ自体が悪いわけではないのですが、「元のラインに馬を戻す」ではなく、「逆方向に馬を曲げる」になっちゃってるんですよ。だからこそ、馬が余計にグラグラするんです。
1膨らんだら1戻す。2倒れたら2起こす。馬体操作には、この感覚が不可欠です。
慌てず、指示をする前に「どれくらいの指示をすれば、自然にこのカーブは曲がれるかな」と考える習慣をつけましょう。車だってハンドルを曲げた分しか曲がりませんし、曲げすぎたら切れ込んじゃいますよ。
馬への指示がしっかりしていても、乗り手のバランスが馬に影響を与えてる場合があります。
バイクなどもそうですが、乗り手が内側に傾いたり外側に膨らんだりしたら、馬も真っ直ぐは歩けません。
特に輪乗りと巻き乗りは、加速と回る角度によっては遠心力もかかります。背中こそ真っ直ぐでも、体ごと重心がズレる可能性があります。
なので、自分が本当に真っ直ぐか確認する基準として、曲がる指示を出していない時のお尻と両足への体重のかかり方を覚えておきましょう。
例えば僕たちは外側に傾いたら、落っこちないように外側の足を踏ん張って、体をその場に残そうとします。
すると、真っ直ぐの時は両足に均等にかかっていた体重が、内側の足の方が軽くなり、外側の足の方に重く乗りますよね。
この感覚を覚える事で、実際に自分がどれくらい傾いているのかを、お尻と両足の圧力センサーを使って確認する事が出来ます。
最初はゆっくりのカーブから、鐙に掛かる重さに集中する時間をとってみましょう。後々も使う技術になるので、時間をかけても良いのでしっかり覚えて下さいね。
左右のバランス確認についての記事はこちら!
これまで手綱を短くするのは、人間の安全と姿勢のために使う事が多かったと思います。
ですが、今回は違います。誘導の際に手綱を短く持つ理由は、本当に小さな馬の変化にも気づくためです。
輪乗りや巻き乗りの他の回でも解説している通り、馬が体ごと思い切り傾いたら、僕たちは間違いなく引き起こせません。
となると、傾こうかな?と馬が思った「瞬間」に対応をするのが、一番小さな力で確実に馬をコントロールできるわけです。
まずは手綱を短く持ち、ハミのかかりを指先で感じられるようにしておきましょう。
その上で、馬が小さくても指示と違う事をしたら、軽く反応を返してあげて下さい。
この段階では、具体的な指示までする必要はありません。「何かしようとしてるでしょ。気づいてるよ。」というつもりで、軽く手招きをして口に違和感を与える程度で結構です。
それ以上に馬が変な行動をし始めたところで、初めて対策に移ってくださいね。
とはいえ、初心者の方にとって一周の円を描くのは、想像以上に長い時間、馬の制御をし続ける必要があります。
軽い速歩でも、10秒くらいはかかるでしょうか?これまでやってきた指示や対応と違い、初めて指示を与え「続ける」項目になると思います。
だからこそ、それだけの時間馬に集中をし続けた経験がない人が、途中でちょこっと気が抜けて、そこから馬が崩れていくパターンが非常に多いです。
これは、徐々に慣れていくしかありません。
よく言われている練習法として、円ではなく細かい四角形を描くと考える練習方法があります。
これまで内方姿勢や隅角通過をやってきた方なら、四角形のコントロールは出来ると思います。四角形なら、直線はいったん休憩し、曲がる時だけ気を張れば良いわけですからね。
これを6角形、8角形と細かくし、徐々に円に近づけていく練習法です。輪乗りや巻き乗りに悩んでいる方は、ひとまず試してみて下さい。
まとめ!
今回は馬上でキレイな円がイメージできないという方へ、その原因と、基準を持つための考え方をお話ししていきました!
全4回の輪乗り巻き乗り講座も、これにて終了となります。長々とお付き合いいただき、ありがとうございます。
輪乗りや巻き乗りを覚えた先の乗馬は、一つ一つの解説が結構長いものになると思います。
それは、乗馬から馬術に内容が変わっていくからです。
ただ好きなようにしている馬に乗るなら、輪乗りや巻き乗りなんて苦しい事をせず、思い切り体を傾けて急カーブを描いてもらえばいいんですよ。
速歩にも制限時速や内方姿勢なんて求めず、体をフルで使う馬にただ付いていけばいいんですね。
でも、それをやられたら、僕たちって馬に乗ってられないじゃないですか。
なので、人間の都合に合わせてもらうために、馬がどうやったら言う事を聞いてくれるかしっかりと理解して、その体勢に導いてあげるのが馬術なんですね。
「馬の事を理解せず、でも人間の言うことを聞いてもらう」というのは無理があります。
そんな事が出来るのは、力ずくで、あるいは恐怖で無理やり馬を押さえつけ、やりたくない事をやらせる騎乗でしょう。ですが、皆さんが求めている騎乗はそのようなものではないと思います。
覚える事は多いですが、時間がかかっても良いんです。何となくでも良いんです。
言う事を聞いてもらうために自分が努力していこうというその姿勢が、馬を扱う人としてのレベルを上げてくれます。
分からない事はお伝えしていきますので、一緒に頑張っていきましょう。
ご覧いただき、ありがとうございました!






