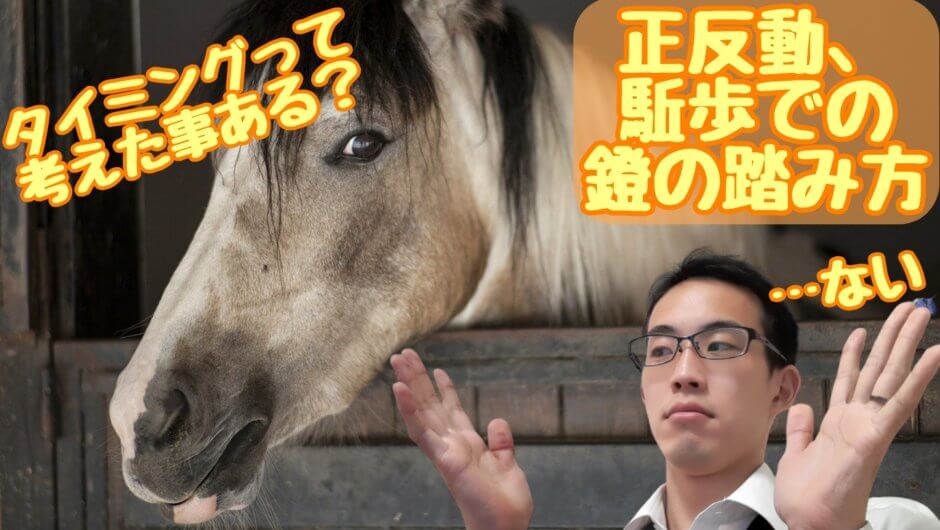かかとを下げるのが大事なのは分かってるけど、正反動や駈歩みたいな体が跳ねる走り方では、弾んじゃってそれどころじゃない!どうすれば良いの?
そんな悩みにお答えします!
これらの乗り方は、座りっぱなしで反動を受ける事になるため、体の芯から浮き上がってしまい、鐙が脱げてしまうんですね。
今回は、正反動や駈歩などといった「体で反動の対処をする乗り方」での、鐙の踏み方とポイントについて解説していきます!
この記事のもくじ 閉じる
前提条件

正反動や駈歩で鐙を捉える場合、その前の前提条件として膝から上だけで随伴が出来るようになる必要があります。膝から下も反動で浮き上がってしまったら、そもそも足が浮いて鐙が履けませんからね。
詳しくはこちらの記事で解説しています。かかとを下げたり扶助をしたり等の脚関係は、一番最後に身に付ける事だと覚えておいてください。
正反動や駈歩での鐙の踏み方
さて、脱力や随伴がなんとなく分かってきたとしましょう。
とは言っても、ただ反動に身を任せていては、鐙に体重を乗せる事は出来ません。太ももまでは随伴で馬に付いていけますが、膝下はブラブラするだけになってしまいます。
では、正反動や駈歩のような、膝下に力を入れると弾んでしまうような乗り方では、どのように鐙を捉えるのでしょうか?
結論、鐙は踏むには踏みます。ただ、踏むタイミングが重要なんです。
馬は速歩以上の歩様になると、背中が弾むようになります。(解説動画01:32秒より)
弾むという事は、ジャンプして体が宙に浮いている時間と、着地している時間が存在するわけですね。
僕たち乗り手は、このように馬がジャンプするタイミングで、下からの突き上げを受ける事になります。この時に鐙を踏んでしまうと、下からの突き上げのパワーが硬くなった足首に伝わり、跳び箱の踏み板を踏んだ時のように体が弾んでしまいます。
なので、馬が空中から地面に着地し体が沈み込む瞬間に、合わせて踏みに行けば良いんです。そうすると、馬の動きと同様に重心を落とす事が出来るので、鞍からはがれずに済みます。
参考映像を見ると、馬の前脚の着地と、騎乗者の鐙を踏むタイミングが同じ事が分かります。
これは、正反動だけでなく、ジャンプと着地を交互に行う歩様全てに共通する項目になります。なので、駈歩や襲歩にも該当してきます。
鐙を踏む時のポイント

ですが、ただ踏めば良いというわけではないんですね。
踏む事で足首に力が入り、バネとなって体が弾むのも事実です。踏む上でも、気を付けるポイントが存在します。
ここからは、鐙を踏む時のポイントを解説していきたいと思います。今回は5つですね。
- 馬の一歩一歩を認識できるようになる
- 力を入れっぱなしにしない
- 膝は上げない
- 無理にかかとを下げる意識をしない
- 鐙は最後に作るもの
1つずつ解説していきましょう。
正反動や駈歩で鐙を踏むためには、馬が跳んでいる時と着地している時を判断できる必要があります。
ですが、初心者の方が乗馬を習うにあたって、ここまでテンポが早い回転って、そうそうなかったと思います。
僕もそうでしたが、最初のうちって、軽速歩の立つ座るですら体が追いつかない方もいます。1.2.1.2の2拍子でもままならないのに、正反動は1拍子で随伴しなきゃいけない訳です。軽いパニックです。
ですが、こればかりは慣れていただくしかありません。非常に大変ですが、その判断速度で余裕を持てるくらいにならないと、正反動で常に鐙を捉える事は不可能です。
まずは頭でリズムを感じるだけで大丈夫です。反動が小さい馬や安心できる馬で、ゆっくり覚えていって下さい。
ただ意外と、この1拍子って難しくないんですよ。「踏む」と「足を上げる」のどちらも筋肉を使わないといけないなら大変ですが、実際には脱力したら、足の位置って勝手に上がるんですね。
なので、常に力を入れっぱなしにするのはやめましょう。
足の力を入れっぱなしにしてしまうと、馬の上下の回転に追いつけず、力が入ってる時に突き上げが来て、体が弾んでしまいます。
鐙を踏む時だけ力を入れてくれれば良いんですね。下に踏みつける、押し付けるというよりかは、バスケットボールのドリブルをするように一瞬押さえるイメージです。踏む、踏む、踏むではなく、押さえる、押さえる、押さえる。といった具合です。
正反動や駈歩をする上で最も重要なのは、座りによる随伴運動です。
しっかり踏む事ばかりに意識を向けた結果、膝が外に開いたり、鞍からはみ出したりしたら、基本姿勢も維持できなくなります。足を上げて、大きく踏みに行く必要はありません。
詳しくはこちらの記事を見ていただきたいのですが、上手くニーパッドを機能させる事が出来れば、膝は上がっていく事はありません。
そして、膝が上がらなければ、僕たちの足は浮く事がありません。鐙が脱げないように、頑張って爪先立ちで引っ掛ける必要もなくなります。
座りを崩さない程度に、膝は下げるだけにしておきましょう。先程も言った通り、鐙は「押さえる」程度で結構です。
正反動や駈歩をする上で、確かにかかとは下がっていた方が良いです。
重心が落ちますし、何より体が数センチ弾んでも、鐙が外れないんですよね。
爪先立ちの場合、足の指先まで下方向にピンと伸びているので、体が弾むと、途端に鐙を踏んでられなくなります。
一方でかかとが下がっている場合は、体が多少弾んでも沈んでいた分が浮くだけで、鐙に指は乗せてられるんですね。鐙が脱げる方にとって、大きな解決策になります。
ですが、かかとって脱力した結果として下がるものであって、下げる!と意識して力づくで下げるものではありません。
階段のフチとかでやってみると分かるんですが、意図的に下げようとすると筋肉が固まって、逆に出来なくなるんですよ。それどころか膝まで伸びてしまって、座る姿勢がメチャクチャになってしまいます。
かかとは、脱力した上で、タイミングに合わせて踏めるようになった結果、自動的に下がるものです。
参考が多くて申し訳ないですが、詳しくはこちらの記事で解説しています。集中したからって出来るものではないので、他の課題を先に解決してしまいましょう。
鐙の踏み方や、かかとの下げ方などの足回りは、胴体の随伴が出来るようになった後、一番最後に行うものです。
乗馬って、競馬乗りのような立ちっぱなしの乗り方をしない限り、胴体が一番反動を受けます。なので、胴体への反動を逃がす姿勢を一番優先しないといけません。
にも関わらず、「鐙を履いてなきゃ!」って思う方って、鐙の優先順位を胴体より上にしちゃうんですね。大丈夫です、僕もそうでした。
先に足の形を作って良いのは、軽速歩やツーポイント騎乗などの、足のバネを使う乗り方をする時です。正反動や駈歩など、胴体で馬に付いていく乗り方において、足の形を優先して体の融通が利かなくなるのはもったいない事でしかありません。
改めて、鐙の長さや踏む位置の調整は、一番最後に行って下さいね。
まとめ!
今回は、正反動や駈歩の際の鐙の踏み方について解説しました!
踏むには踏むけどタイミングがありますよ。また、座る姿勢ならではのポイントがあるよ。という話でしたね。
鐙を踏む、かかとを下げるのは重要ですが、とても難易度が高いです。理由は、「脱力しながら体重をかける」という正反対の行動を、同時にやらないといけないからです。
そのため、すぐには覚えられません。僕自身も、これがきっかけで覚えられた!というのは覚えてないです。強いて言うなら、競走馬という背中が非常に敏感な馬に乗って、「本気で背中に圧をかけちゃいけない」という環境に置かれたから身に付いたものです。
まずは馬に乗りながら、「こうかな?それともこうかな?」と考えられるくらい、余裕を持てるようなりましょう。
その上で、たくさん試行錯誤をしていって下さいね。
ご覧いただき、ありがとうございました!