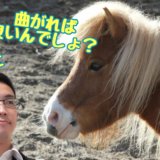ドカドカ座るなって言われたけど、鞍って座るものじゃん。上手い人だって、みんな座ってるし、言ってる意味が分からない…!
そんな疑問にお答えします!
今回は、馬の上での体重分散について解説します!
この記事のもくじ 閉じる
体重を分散する理由
馬の背骨は、前脚の骨と、後ろ脚の間に、吊り橋のように位置しています。
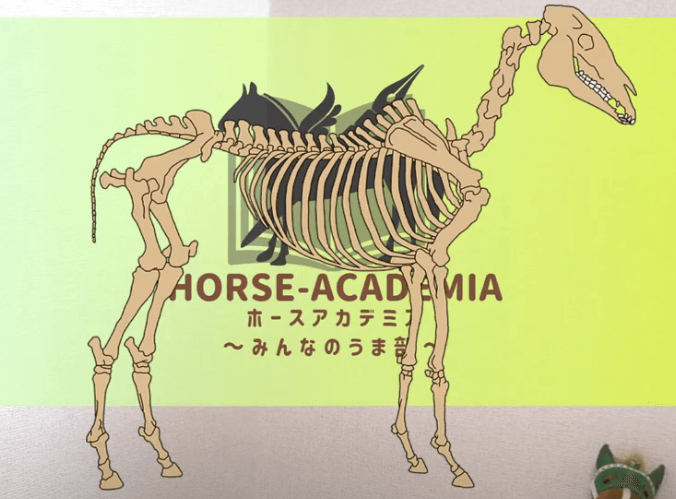
この背骨の周りを、たくさんの強い筋肉が支えてるから、僕たちは乗る事が出来るわけですね。
ところが、背中の一点だけに体重をかけると、馬は人間を支えられなくなってしまいます。
吊り橋の真ん中で、大きくジャンプを繰り返したら、橋全体がたわんで最悪折れてしまいます。それと一緒で、いくら強い筋肉に守られてるとはいえ、背骨に思い切り座るのは、馬のダメージになるんですね。
鞍が持つ分散効果
でも、僕たちは馬に乗っています。それは、鞍に助けられてるからです。
鞍を裏返しにすると、背骨の周りを避けるように、空洞と、パッド部分があります。このパッド部分の事を、鞍じょくと言います。英語でパネルとも言います。

このパッド部分が、鞍の一番前から、一番後ろまで伸びている事で、人間の体重を、背骨を避けて背中全体に分散してくれてるんです。
お尻だけに頼らない座り方
ただそれでも、お尻だけに体重を乗せたら、そのお尻の場所によっては、クッションがヘタってきたり、比重が偏ってきたりします。
鞍は、固定されてると言っても腹帯だけでしか止まってません。思い切り後ろに座ったりしたら、後ろに傾いていくんです。これでは、腰の骨の圧力が強くなるだけで全体に分散は出来ません。
では、どうすれば良いのでしょう?
答えは、「鐙にも体重を乗せる」です。
鐙を通してる鐙革は、鞍の中の鞍骨というパーツに繋がってます。これは、鞍の形を決めるプレートで、鞍全体に通ってるんですね。

なので、鐙を踏むという事は、鞍全体を、下に押し下げるという事なんです。そうすると、お尻で乗ってる時より、背中全体に体重が分散します。
馬の背中を軽くしてあげる乗り方として、ツーポイントという、お尻を上げた乗り方をするのも、これが理由です。あれは、体重を軽くするという意味ではなく、背中全体に体重を分散させる事で、馬が楽に人間を背負えるようになる姿勢なんですね。
僕たちが基本的に行っている座り方は、これに対抗して、スリーポイントと言います。ツーポイントでは、両方の鐙という2点で体重を支えていたのが、そこにお尻が加わって3点になったからです。
ただ、しっかり座ってしまう方の多くが、スリーポイントではなく、お尻だけのワンポイントになってしまうんです。これが、「座るな」という言葉の意味になります。
お尻だけに体重を乗せていると、馬の背中を痛めるし、動きにくいし、乗り手もバランスを崩しやすいから、しっかり体重を分散しなさいという意味だと思います。
具体的なポイント

さて、ここまでで既に、鞍の知識、馬の体の知識、乗り方の知識と、多くの事をお話ししています。
なので、具体的なポイントについては、簡単に2つだけにしたいと思います。
- 随伴に合わせて鐙を踏む
- 脚全体に、体重を乗せる
なお、完璧な体重の分散は、騎座の操作という高度な技術が出来て、初めて出来るものです。一度に理解出来ないのが普通なので、時間をかけて感覚を覚えていって下さい。
馬と一緒に重心を下げる事で、お尻が跳ねないようにする方法ですね。
そうする事で、鞍の一番深い所からお尻が離れるのを防ぎ、重心が鞍の前後に偏らないようになります。
詳しくはこちらの記事で解説しています。興味があれば、ご覧ください。
膝だけ、股関節だけという、一点だけで全部の体重を処理しようとするから、その一点だけに依存してしまいます。
お尻に2、股関節に2、太ももに2、ブーツに2、鐙に2と、下半身全体を使って、鞍や鐙に体重を乗せるようにしましょう。
個人的には、挟むというよりは、鞍からズレないという認識の方が良いと思います。
経験出来る方は少ないと思いますが、鞍を乗せない状態の馬に乗ったら、誰もが自然とこうなります。支えてくれる場所がないからと、足全体を体に添えるこの乗り方が、本来の乗り方なんですよ。
こちらの記事が、参考になると思います。興味があれば、ご覧ください。
まとめ!
まとめ
今回は、鞍の効果と馬の体の仕組み、体重分散についてお話ししました。
4級ライセンスを越えたくらいの内容になりますね。人によっては、少々難しかったと思います。
今回の内容が難しかった人は、お尻だけでどっかり座っちゃいけないのね。とだけ覚えておいてくだされば大丈夫です。
それが、軽速歩の立つ座るや、駈歩の随伴などに繋がっていきます。
ただもし、4級ライセンス以上、あるいは馬体操作を覚えるのであれば、この考え方は覚えておいた方が良いと思います。
というのも、背中にどっかり座っているだけで、自分から馬にとっての負担を作ってる事になりますからね。
背中の人間が、自分と同じくらいに体を使えるから、馬も動きやすくなります。特に障害馬術では、上の人が馬より動きが遅いのは、ちょっと大きなデメリットになります。
これは、蹄跡を歩いたり走ったりする、準備運動でも確認できる項目です。お尻の体重センサーという、新しいセンサーを作れるようになりましょう!
ご覧いただき、ありがとうございました!
お知らせ!
youtubeにて、ホースアカデミアの部員を募集してます!
有料にはなってしまいますが、馬の知識を
さらに深められるサービスです!
興味がある方は、以下の記事をご覧ください!
有料メンバー(部員)のご案内