
鞍から膝がはみ出ちゃう…。鞍が小さいのもあるかもしれないけど、言われてみれば足が長いとも言われる。足が長いのはメリットって聞いたけど、実際どうなの?
そんな疑問にお答えします!
乗馬において、足が長いのはメリットだと言われてます。実際、多くのインストラクターが同じ事を言っているのを聞いてきました。
ですが、乗馬において足が長い事は、残念ながらデメリットにも成り得ます。
今回は、足が長い事によるメリットとデメリットについて解説していきますね!
足が長いメリット
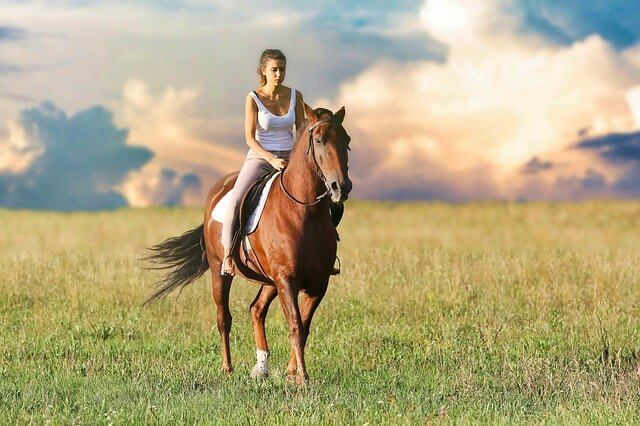
足が長いメリットは2点です。
- 脚合図をより下から使える
- 深く座る事ができ、姿勢が安定する
解説しますね。
鞍に座っているお尻から足が長く下に伸びていれば、その分かかとの場所も下に下がりますよね。
という事は、脚合図を通常より下から当てる事ができ、より強い刺激を与えたり、馬が体を起こす運動をサポートしたりできるんです。
特に駈歩などの、「体を持ち上げて走る歩様」になった時、これは役に立ちますね。
足が長い分、より馬の体を大きくキャッチするため、鞍からはがれずに座る事が出来ます。
そもそも足が短い人と比べて、最初から体重の比率が違うんですよね。僕なんかは上半身60の下半身40くらいだと思いますが、足が長い人は上半身40の下半身60くらいだったりします。なので、上半身が跳ね上げられないんですよ。うらやましいですね。
正反撞速歩という、座ったままで走った馬に乗る乗り方をした際は、この差が顕著に出てきます。
足が長いデメリット

一方で、デメリットも2点あります。だいたい想像がつくと思いますが、両方とも、メリットがそのまま弱点になります。
- 脚合図が強力になりすぎる
- 膝が鞍に収まらない
解説しますね。
足が長すぎるがために、普通に足を曲げただけでも、脚合図がお腹の後ろに当たってしまうんですね。
また、足が長い方は必然的に鞍に深く座る事になるので、悪い意味で馬を上からプレスしちゃいます。
そうすると、敏感な場所を下から蹴られたにも関わらず、上方向に体をすくませる事も出来ない馬って、真っ直ぐ前に走っていくんですよね。
なので個人的な経験として、足が長い人は、「なんでか馬が元気になっちゃうんですよねー」という悩みを持っている方が多いです。
とはいえ骨が縮むわけでもありませんし、足を短くは出来ませんからね。意図的に合図を弱くする事で、改善していきましょう。
また、座りが重すぎる点については、今後記事を作っていきますので、そちらをご覧ください。
これが、足が長い人の最大のデメリットだと思います。
普通の鐙の長さや、鞍の形だと、足が収まりきらないんですよね。
鐙革をすごい長くしたら、足が真っ直ぐになっちゃうので、ニーパッドが機能しません。
だからと言って通常の鐙の長さにすると、膝が鞍からはみ出てしまいます。
1本1本の骨が長いんですよね。つまようじを真ん中で折るのと、箸を真ん中で折るのとでは、当たり前ですが箸の方が折れても長いです。
なので、乗馬施設で貸し出している鞍ではサイズが合わない事があります。別個で大きい鞍か、馬場鞍という、足を伸ばして乗る鞍を薦められる事が多いです。
軽速歩という、立ったり座ったりする乗り方が苦手な場合が多いです。足の位置が定まってないのに、重心の移動をしたら、バランスは崩れますからね。
僕がレッスンするとしたら、まずは座りっぱなしの正反撞を覚えていただき、何かあったらこの乗り方をすれば良いやという安心感を作ったうえで、軽速歩の練習をしてもらいます。
まとめ!
今回は、足が長い人のメリットとデメリットについてお話をしました。
こればかりは、レッスンでは直せませんからね。
かくいう僕も足が短い人間なので、正直言って具体的な対策が分からないんですよね。
何かアドバイスをお持ちの方は、コメントなどで教えてくれると嬉しいです。
ただ、最初に言った通り、これは上手い下手ではないんですね。体の構造上、どうしても出てきてしまうものなんですよ。
なので、ちゃんとそれを理解してくれる人の下で教わりましょう。教科書や、上達の流れがこうだから、出来るまでやる!という不思議な都合で、貴重なお金や時間を無駄にしないようにしてくださいね。
ご覧いただき、ありがとうございました!



