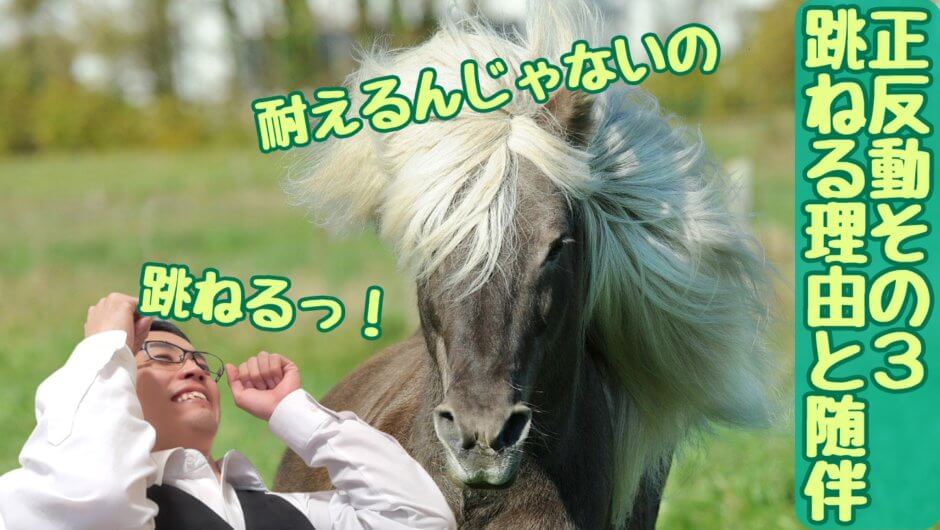馬は良い子にしてくれてると思うんだけど、正反動をしてるとどうしても体が跳ねちゃう。なんでだろう?
そんな疑問にお答えします!
仮に皆さんの姿勢が素晴らしかったとしても、結局体が跳ねてしまっていたら、「これで良いんだ」とは思いませんよね。
今回は、僕たちは正反動中どうすれば良いのか、どうなっていれば正解なのかについてお話をしていきたいと思います!
その1、その2はこちら!
この記事のもくじ 閉じる
なぜ正反動では体が弾むのか

いきなり本題ですが、どうして正反動では体が弾んでしまうのでしょう。
結論だけ言いましょう。「受け流せる姿勢がとれていないから」です。
正反動で体が弾む直接の理由は、お尻に直接反動を受けているからです。馬に乗って正反動をしていれば、初めて乗った人でも、オリンピック選手でも変わりません。
ですが上手い人の騎乗を見ていると、正反動をしているにも関わらず、馬の口に入っているハミはガチャガチャしていません。となると、跳ねるという衝撃を、お尻から腕の付け根である肩の間でどうにかしているという事になります。
興味深いのは、こちらの映像です。
これはパラリンピック馬術の競技動画ですが、彼女は生まれつき両足がありません。ですがご覧の通り、見事に正反動をこなしています。
正反動に必要なのは、足でしがみつく事でも、体重をかけてしっかり「座る!」と意識する事でもなく、反動を受け流せる姿勢がとれるかどうかなのです。
キレイな姿勢という勘違い
ここで1つ、皆さんに質問をしましょう。骨って、縮むと思いますか?
すぐに分かりますよね。もちろん縮みません。
では、もう一つ質問をしましょう。骨が縮まないのに、体を真っ直ぐにしてどうやって下からの突き上げを受け流すんですか?
そうなんです。出来ないんですよ。ここが、正反動に悩む方の大きな認識の違いなんですよね。
姿勢を正しくって言われた。坐骨を立ててって言われた。馬場馬術の選手がそう乗っていた。皆さんそうやってとても真っ直ぐな、キレイな姿勢で馬に乗ってくれます。
ですが、僕から言わせればそれが、皆さんが正反動が出来ない理由なんですよ。あまりにも真っ直ぐに乗るものだから、下からの突き上げをまともに芯に受けて、体から弾んでいくんです。
「真っ直ぐ」と言えども、それはあくまで姿勢であって、実は随伴は真っ直ぐじゃないんですね。これが、僕たちを誤解させるポイントです。
反動を抜く方法
改めて、騎乗中は下から反動が来ます。
そして僕たちは骨を縮める事は出来ません。突き上げを下から受けているうちは、どうにも対策は出来ません。
では、どうすれば反動を受け流せるのか。
答えは「前後運動に変えてしまう」です。
僕たちの骨格は、上下にこそ伸び縮みはしませんが、前後に動かす事は可能です。フラフープなどはその応用ですよね。
胸の下から太ももの骨の一番下まで、広い部分を使った随伴をする事で、下から上への突き上げを後ろから前への押し込みに変換してしまうのです。そうすれば対応は可能です。
随伴のポイント

とはいえ、言ってる事は分かると思うんですけど、具体的な体の操作が分からないと思います。
そこでここからは、上下運動を前後運動に変換する際の考え方を4つ紹介していきます。
- 初心者は多少骨盤を寝かせるのも可
- 鞍から「はがれない」イメージをする
- 固定するのは「肩」
- 基本姿勢をしっかり作る
解説していきましょう。
最初に言っておきます。初心者の方用の対策ですね。
上下の反動を、骨盤を寝かせる事で前後の腰の動きに変え、感覚を覚える方法です。
体を後ろに傾けたり、鞍にべったりお尻をつけたりした方が、確かに鞍にはまってる感覚がするし、実際に弾まないんですよ。僕も初心者の時はずいぶんこうしていました。
斜め上にお腹を引きこむと指導をする方がいるのもこうした理由からです。
上下の随伴は出来ず、鞍にお尻をこすりつけるような随伴じゃ反動は消せない。だからその随伴を、骨盤の角度を寝かせる事で、斜めにして反動を抜くという方法です。
ですがこの乗り方は、馬のお尻を押し込んでしまうため、後ろ脚を踏ん張らせ、馬を加速させる原因になってしまいます。
また、体を後ろに倒した状態で馬に加速をされると、僕たちの上半身は加速に押し込まれ戻ってこれなくなります。
あくまで初心者の方が、馬に合わせて体を動かすという感覚を持つまでの、応急措置としておきましょう。
馬の背中は、弾んで常に上下動しています。例えばこの揺れが50cmだったとしましょう。
僕たちは正反動など座りを意識すると、どうしても下方向に体重を落としに行く事だけを考えます。僕たちにとって、それが日常的な「座る」ですからね。
ですが乗馬の「座る」は、日常生活の「座る」とは違います。乗馬の座るは、最終的には一体化したような状態になれるよう、馬の動きに常に付いていく事を言います。
なので、皆さんの中で言葉選びを変えましょう。「鞍に座る」ではなく、「鞍からはがれない」にイメージを変えてみて下さい。
0.1秒でも長く鞍からはがれないという意識をするだけで、意外と馬に付いていけるようになるものですよ。ぜひ、試してみて下さいね。
多くの方が、正反動時に固定するのは「腰」だと考えます。腰という幹をしっかり立て、キレイな姿勢を作り、どんな揺れにも負けないようにしていきます。
ですが、馬に随伴をするにあたって、馬の背中に合わせて一番柔軟に動いてなきゃいけないのが腰なんですよ。現に皆さんも常歩の随伴の時は、腰を固めるなんて意識はしてなかったと思います。
でも、弾む馬の上でどこにも芯を持っていなかったら、飛んで行っちゃうという不安も分かります。
そんな方に言いたいのが、「固定するのは肩」という事です。
僕たちは正反動をする上で、自分の体の弾みを馬に伝えてはいけません。体の揺れに合わせてハミがガチャガチャしていたら、背中へのショックも合わせて馬は走りたくなくなってしまいます。
となると、どんなに体が弾んでようと、「腕」という場所は落ち着いてなきゃいけないんですね。
肩を支点にし、振り子のように腰を使っても芯を保てるようにしておきましょう。
常歩の随伴で、腰だけ動かすという感覚をつかんだり、手綱を引っ張っても大丈夫な馬で、指の重さを一定にしたまま随伴をしてみたりする事で練習をする事が出来ます。
別の記事でお話しする「駈歩」などもそうですが、馬上で体を前後に使う随伴は、この先も多く出てきます。焦らず、感覚をつかんでいきましょう。
当たり前の事ですが、一番重要な事です。
これまでの話した通り正反動の騎乗は、体全体を使って反動を受け流す必要があります。
なので、馬体にしがみつき筋肉をガチガチにしていたら、絶対に上手くいきません。下半身を鞍にはめ、力を入れなくても馬に付いていける状態を作っておくべきです。
基本姿勢については、こちらの記事で解説しています。
このように、ある程度先の技術に行っても、基本は大切なものです。皆さんは大丈夫だと思いますが、目先の課題だけに流されないで下さいね。
まとめ!
今回は、正反動中に僕たちが弾む理由と、その対策についてお話をしました!
次回は今回お話しした事をベースに、バランスと姿勢の考え方に付いて解説していきたいと思います。
今回お話しした内容は、1回のレッスンで簡単に身に付くものではありません。
実際僕も、教えるレベルまで行ったかな?と思えるようになったのは、現役競走馬に乗って、座りが馬に与える影響を知ってからでした。なので、仕事で毎日馬に乗っていたのに3年くらいかかっています。
ですが、正反動の重要性を知ってからは、数か月で身に付きました。その時に考えた事や、なんとなくでも身に付いた今だからこそ伝えられる事もたくさんあります。
ぜひ、皆さんのお力になれればと思っています。よろしくお願いいたします。
ご覧いただき、ありがとうございました!
その4はこちら!