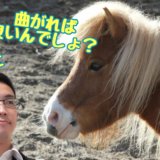誘導の練習を始めたけど、開き手綱と押し手綱という方法を習ったよ!どっちをどんな時に使うの?
そんな疑問にお答えします!
この2つを明確に意識して使い分けられる方って、あまり多くないように思えます。
今回は開き手綱、押し手綱の説明と、その使い分け方について解説していきます!
この記事のもくじ 閉じる
開き手綱

曲がってほしい方向に顔を向けてもらえるよう、内側の手綱を横に開き、ハミをかける方法です。
勘違いしないでほしいのは、横に引っ張るから曲がっているわけではないという事です。
「引っ張られた方向に頭を持って行った方が、口が痛くないよ」と導くための手綱です。車でいう、ウインカーの役目ですね。
横に引っ張る方法もあるにはありますが、引っ張られて口が痛いと感じた馬は、逆方向に引っ張り返してきたりします。曲がらなかったらもっと引っ張れば良いという勘違いはしないようにしましょう。
「脇や肘が開いてしまうから、開くのではなく後ろに引く」という方もいますが、個人的には開くで良いと思います。
引っ張る以上に「前」というパワーを持った馬や、小さい動きでも反応する馬なら話は別です。ですが初心者が乗るような、パワーや芯が無い馬を後ろ向きに引っ張るのは、前向きのエネルギーを打ち消す悪影響にしかなりません。
ただ、思いっきり曲げたいからと大きく腕を開いた時に、とっさの事があるかもしれません。
腕を開くとしても、馬が曲がり始めた時点で基本の位置に戻すようにしましょう。
この時に意識してほしいのは、曲がり始めた時のハミのかかりを持続させたまま、拳を元の位置に戻す事です。戻す事だけに集中して最短距離を移動すると、せっかくの手綱の張りが一瞬緩んでしまいます。
言う事を聞いた時の手綱の張りと指の重さを保ったまま、少し遠回しに戻すようにすると、腕を基本の位置にしたまま効果を継続できますよ。
押し手綱
曲がってほしい方向と反対側に手綱を巻き付け、馬を押し込む方法です。基本的に、外側に押し出す時に使います。
開き手綱は導く手綱と言いましたが、押し手綱は、実際に力を加える手綱です。
ハミのかかりというウインカーを与え、首というハンドルを曲げても、前脚というタイヤが曲がらなければ馬は曲がりません。
そんな馬の車体を押し込み、人間の力でタイヤを曲げるサポートをするのが押し手綱です。
この押し手綱、拳の高さによって、手綱が巻き付く場所が変わります。
馬の口より拳を上げて使うと頭蓋骨付近に作用し、拳を下げて使うと首の根元や肩のあたりに作用します。初心者の誘導は、前脚を横にずらして曲がってもらう運動になるので、拳は下げて使って下さい。
馬の体重を押し込まなければいけないので、意外としっかり使う必要があります。中には軽く当てた程度で反応してくれる馬もいますが、だいたいは強く使う事が多いです。
とはいえ、押し手綱だけで馬の体重を押し返すのは人によっては難しいです。別の記事で話す内方脚なども使って、馬を動かしていきましょう。
ポイントは、手の甲を下にして押し込む事です。
手の甲を上にして押し付けると、ボクシングのフックみたいに肘が開くんですね。あと、強く押し込もうとすると体がねじれていきます。
そうではなく、刀を持って内側に切りつけるように、肘を内側にして使いましょう。
ただ、腕が馬のタテガミのラインを越えると、こちらも体がねじれてしまいます。そうなる前に手綱を短く持ち直し、踏ん張れるようにしてくださいね。
なぜ使い分ける必要があるのか

2種類の手綱の使い方を紹介していきました。
ですが、両方とも「曲がって」という指示なら、どちらか片方だけを使い続けていても問題は無いように思います。
ではどうして、押し手綱と開き手綱を使い分ける必要があるのでしょう?
それは、馬には2種類の曲がり方があるからです。1つは体を曲げるカーブ、もう1つは体を傾けるカーブですね。
自転車を想像していただけると分かりやすいと思います。ハンドルを曲げても自転車は曲がりますが、車体を内側に傾けても同じように曲がっていきますよね。
これと同じ事を馬もやっています。首や体を折り曲げてカーブを曲がる方法もありますし、片側の脚に体重を乗せ倒れるようにカーブする方法もあります。
なので、それぞれの曲がり方用の指示として、手綱の指示も2つ種類があるんです。
※曲がり方の詳細はについてはこちらの記事をご覧ください。
どのような時にどちらを使うのか
結論だけ言うと、開き手綱は体を曲げる曲がり方、押し手綱は体を倒す曲がり方の指示に使います。
逆に使うと、あまり効果が無いんですね。体ごと倒れに行った馬を口だけで釣り上げても、口が痛いだけで逆効果ですし、体を曲げた馬に押し手綱をしても、体の湾曲を余計に助けるだけになってしまいます。
初心者の誘導レッスンでは、基本的には開き手綱で誘導指示をして、内側にショートカットをしてしまう馬に限り押し手綱で体重を押し返す事が多いです。
応用編として、内側の開き手綱だけじゃ曲がってくれない馬に、外側からも体重を押し込みに行く事で、曲がる一歩を踏み出させるという方法もあります。
また、押し手綱だけじゃ外側にズレてくれない馬に、外側からの開き手綱を併用する事で、外に行ったら引っ張られないという逃げ道を与え、動かす事もあります。要するに、両方を同時に使う事もあるという事ですね。
詳細は別の記事で話しますが、誘導の基本となる内方姿勢も、開き手綱と押し手綱の両方を同時に使う技術です。
まずは誘導の練習から、馬の体勢の判断や指示の判断に迷わないようになっていきましょうね。
まとめ!
今回は押し手綱と開き手綱の説明、それぞれの使い分けについて解説をしました!
片方だけじゃ完全に機能はしないんですね。もう片方と併用して使う事で、初めてちゃんとした効果を発揮します。
この2つの手綱の使い方に合わせて内方脚や外方脚などを使う事で、やっと馬体の制御が成立します。
今回の内容は、隅角通過、蹄跡行進、駈歩発進などに繋がる非常に重要なものです。
何回でもチャレンジして、判断に迷わないようにしていきましょう。
ご覧いただき、ありがとうございました!