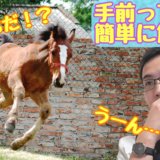手前合わせっていうのを習ったけど、気づいたら逆って言われるし、正直よく分からない…。どんな効果があるの?どう見分けるの?
そんな疑問にお答えします!
今回は「軽速歩の手前合わせ」について解説していきますね!
なお今回の記事は、先にこちらの記事を読んでいただくと内容の理解が深まります。興味があればご覧ください。
この記事のもくじ 閉じる
手前合わせとは?

手前合わせとは、軸足の着地に合わせて立ち座りをする事で、馬の踏み込みを助ける技術です。
馬に限らずどんな動物も、カーブを曲がる時は、内側に体を傾けます。馬の場合は内側の前脚を踏ん張る事で、自分の体を支えてます。
ところが僕たちが、踏ん張りたい脚と別の脚に体重をかけてしまうと、馬はバランスを崩したり、脚をくじいたりするんですね。
なので軸足の着地と、一番人間の体重がかかるタイミングを合わせ、馬が踏ん張りやすくなる為のお手伝いをする必要があるんです。
じゃあ軽速歩中、どのタイミングが一番馬に負担がかかるかというと、僕たちが立ち上がる時なんですよ。立ち上がる時って、自分の体重を持ち上げるくらいに鐙を下向きに踏まないといけないじゃないですか。
もともと支えてる体重に、さらに鞍を押しつける力が加わるわけですからね。よほど思いっきり座りに行かない限り、立つ時の踏ん張りの方が、馬の脚には負担がかかります。
左手前(左ジャンプ)で走ってる時は左前脚、右手前(右ジャンプ)で走ってる時は右前脚が軸足です。軸脚の着地に合わせて立つ事で、馬が地面を捉えるお手伝いが出来ます。
また、軸脚の着地に立つ瞬間を合わせる事で、人間の立ち始めと、内側の後ろ脚の蹴り出しを合わせる事が出来るようになります。馬自体の前に行くエネルギーを邪魔しないという効果もあるんですよ。
手前の確認方法と、合わせるコツ
手前の確認方法と、合わせるコツは以下の通りです。
- 内側の前脚を見ておこう
- 立ち終わりと、手前脚の着地を合わせよう
なお、そもそもの立つタイミングについては、こちらの記事で解説させて頂いてます。
今回は、間違っていないかの確認方法について解説しますね。
当たり前ですが、基準となる脚がいつ着地しているかが分からなければ、立ち上がるタイミングも分かりません。
軸足の着地を、しっかり目で追えるようにしましょう。
教える人の中には「下を見ない」という人も居ますが、手前合わせの練習に限っては気にしなくていいと思います。目に見えてハッキリ基準があった方が、確実に早く覚えられますからね。
感覚をつかんでから、見ないようにすれば良いんです。手前を確認するだけに集中して、まずはちゃんと覚えてしまいましょう。初心者の方が乗せてもらう馬は、それくらいで走りだしたりはしません。
もちろん、前のめりになりすぎないようには気を付けて下さいね。
蹄まで見るのが怖ければ、前脚の付け根の筋肉が盛り上がった瞬間に立ち始める事で、タイミングを合わせられますよ。
軸脚の着地と同時に、僕たちが立ち「終わる」事が肝心です。
「立ち上がり始める」じゃなくて、立ち終わって姿勢が一瞬ピタッと止まるタイミングを、馬の着地と合わせましょう。
そうする事で、全く同じタイミングで地面を踏みしめ、全く同じタイミングで筋肉に芯を持つ事が出来るようになります。ぜひ試してみて下さい。
教える人の中には、外側の脚が前に出たと同時に立ち上がると教える方も居ますが、やってる事と最終的なタイミングは同じです。そっちで覚えている方は、特にやり方を変える必要はありません。
ただ、どこで「前に出た」と感じるかは、人によって判断基準が大きく違います。
動き始た瞬間、「動いた!」と立ち始める人もあれば、首の真ん中くらいまで脚を振りかぶってから立ち始める人も居て、ちょっと曖昧かなと思います。
着地という一瞬に基準を合わせた方が、タイミングとしてはつかみやすいのかな?と個人的には思います。
実際にやってみて、自分の感覚に合う方を選んでください!
まとめ!
今回は、軽速歩の手前合わせについてお話ししました!
手前合わせは、乗馬のステップの中で最初に出てくる「馬のための技術」になります。
この先、ある程度馬に乗れるようになると、どうやったら馬に乗ってられるかという人間目線ではなく、どうやったら馬に動いてもらえるかいう馬目線にレッスンが変わってきます。
そこが、乗馬と馬術の明確な境目になります。手前合わせは、初めての「馬術」なんですね。
自分の事だけでなく、馬にも視野が向くようになって、初めて出来るようになるのが馬術です。
それは、どの種目や乗り方になっても共通するものです。遅かれ早かれ馬の能力や可能性をもっと引き出してみたい人は、学ぶことになるものです。
ぜひ、馬を理解してパートナーになっていくまでの道のりを楽しんでいってください!
ご覧いただき、ありがとうございました!